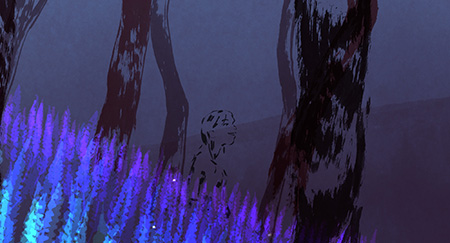──世界の人々に長編を観られる機会を得て、作家としてのスタンスが変わったりはしませんか?
「以前は短編を1本1本すべて違うスタイルでつくっていました。それらは様々な映画祭で上映されてきましたが、同じ人物がつくっていたことに気付いた観客はいないんじゃないかと思います。たとえば山村浩二さんや、ユーリー・ノルシュテインさんなら、作風が定まっているので、同じ作家がつくったことがわかりますよね。これまでのつくり方は自分のキャリアにとって、ポジティブなことではなかったと思います。この作品を機に状況が変わりました」
──どう変化したんでしょう?
「この作品と同じ作風を続けたいと考えています。これから作品に触れる観客が、これは私という作家がつくったんだと発見できる、そんな作品をつくりたい」
ここには自分の居場所がある
──新たな指針が立っても変わらないのは創作の喜びや面白さだと思います。アニメーション制作の一番の醍醐味は?
「わからないです(笑)。そもそもアニメーション作家になったのも偶然ですから。初めてつくったのは学校の修了作品で、日記をもとに実験的なつくり方をしたもの。ある映画祭で上映されて評価をいただき、やがてフランスのアニメーション映画史にとって重要な作品と位置づけられるまでになったんです。私はもともとバンドテシネ(フランスの絵画調のコミック)が好きで、尊敬している作家がたくさんいます。でも、その中に自分の居場所があるとは思えなかった。ところがアニメーションには自分の居場所があると感じたんです。当時、25歳でした」
自分より強い何かに導かれて歩んできた道
──現在45歳ですよね。よく作家活動を続けられましたね。
「『もうやめたい』と思う瞬間は定期的に訪れています。その都度、プロデューサーたちが『作品をつくらないか』と話を持ちかけてくれたおかげで続けて来られたんです。そんななか、『~手をなくした少女』は、新しいドアを開いてくれました。最近になって初めて『アニメーションをもっとつくり続けたい』と思うようになったんです。そういう意味で、自分がたどってきた道のりは不思議なものです」
──「不思議」ですか。
「数年前、あるプロデューサーが『「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ」という長編企画をやらないか』と持ちかけてきました。キャリアを考えれば受けるべきなのに、なぜか私はすぐに断ってしまった。企画は別の人が引き受けたんですが、予算も潤沢だったし、結果的には興行も評価も大成功を収めた。セザール賞(フランスにおける権威ある映画賞)にノミネートされたほどです。その間、私は何をしていたかというと、短編を2本つくって、そのうちの1本は世界の映画祭で上映されることになりました。どちらが重要だったか………それは言うまでもありません」
──こちらの道が正しかった、と。
「私の人生は常に、何かわからない、自分よりも強いものに導かれてきた気がします。過去に決断してきたことが自分に何をもたらしてくれたのか。それらは、後になって発見できるものなのではないでしょうか」
──運命を信じて、縁に導かれて、創作を続けているんですね。
「そうです。まったくそうだと思います。みなさんは違うんですか?」
2018.8.17
[photo]久田路 [text]八王子真也
sébastian laudenbach |
|
大人のためのグリム童話 |